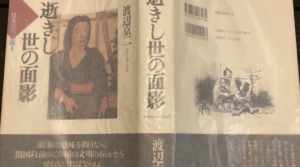この春、「いつかこんな暮らしがしてみたい」の理想の場所に引越すことができました。
畑付き、田んぼ付きの築122年の古民家です。昨年は拠点を持たず、あちこちでイベントを行いましたが、今年は新潟県三条市の住まいを拠点に活動をします。
上映会などの大勢が参加するイベントなどは拠点の近場で開催できたらなと思っています。
畑で作物を育てたり、かまどを作ったり、竹炭づくり、味噌をはじめとする発酵調味料づくり、郷土料理を作る会などをワークショップ形式で開催します。
大人が本気で遊ぶ
子ども向けの遊びを用意するのではなく、まずは大人が本気になる、そして子どももつられて遊ぶの場にします。
畑を一緒に耕して作物を収穫して調理して食べたり、“週末縄文人”の二人を参考に石器づくりや土器づくりなども行いたいです。
家の敷地の土中環境改善活動や池だった場所の整備(石垣を崩して玄関前の飛び石に変える)と、土間にかまどを、畑の真ん中に竪穴式住居を作ってみたいなと思っています。
“土中環境”とは、国内外で造園・土木設計施工、また環境再生を行ってきた高田宏臣さんの取り組みがきっかけとなって広まりつつある用語です。
大規模な土砂災害が多発しているのは、アスファルトやコンクリートによって地中の空気・水の循環が遮断され、地中が乾き、水がしみこまなっているのが原因とされています。
空気と水の循環がうまくいくように空気穴や溝を掘ったり、炭や竹などを埋めて地中が呼吸しやすいようにする造作などがあります。
表層5cmを改善するだけで土中は改善すると映画『杜人』の環境再生医・矢野智徳さんは言っています。
雨水の浸透と共に、空気も土中に引き込まれて、それによって土中のあらゆる生物活動が健全化し、さらに土壌環境は連動的自律的に豊かに育まれていきます。

目指すは百の仕事ができたというかつての百姓
自然のサイクルとともにあった年間を通しての農作業や暮らしは、豊かな経験と生きる技術の宝庫です。家電が家庭に普及する前(1950年代頃まで)、当たり前に各家庭で作られていた塩漬けやひもの等の保存食や、味噌や醤油等の発酵調味料を子どもと協力して仕込んだり、畑を借りて農薬や肥料は使わない栽培方法で子どもと楽しみながら畑仕事を行い、収穫を目指します。その頃の暮らしを覚えているメンバーの祖父母(お年寄り)から郷土料理や縄ない、山菜摘みなども教わる予定です。

自然の中で思い切り遊ぶ=子どもの成長に欠かせない経験
子どもだけで考え・決定・実行することは、子どもの自信に繋がります。大人がすることは、環境を用意して子どもたちを見守ることです。焚き火をして鍋でごはんを炊いて、魚を焼いて、味噌汁を作って火を囲んで食べることなども当たり前に出来る子どもを育てます。

親子のコミュニケーション、四季折々のお手伝い
かつての家庭には、四季折々に子どもの仕事がたくさんありました。水汲みや薪運びをして風呂を焚くというようなことも子どもの仕事でした。家の中や外の掃除も子どもに任されることが多かったと言います。小さいきょうだいの世話や、食事の支度を手伝うことも当たり前でした。家庭での仕事は、大人の真似をして身に付けていくものですから、まず大人たちがそれらの仕事を身に付けなくてはなりません。子どもなりに暮らしに参加することは、家族の一員としての貢献感を得られる機会ですが、現代ではその機会が失われています。子ども達に貢献感や自己重要感、自己肯定感が育つためには暮らしの中に子どもの役割を取り戻さなければならないと考えます。

年中行事・イベント
昨年と同様、お互いの顔を見てのコミュニケーションを大切に、除菌ではなく様々な菌と共存すること、てづくりの美味しいものをたっぷり食べて免疫力旺盛な身体づくりをすることを目標に様々なことに挑戦します。
築122年の住居兼拠点で畑をして作物を収穫したり、広い庭に竪穴式住居を作ったり、ドラム缶風呂をしたり、鶏を飼ってみたりしたいです。
大きいイベントとしては、春は運動会・夏は川や海で遊び・秋は収穫祭・冬はプチ上映会などを行います。

子ども自身が自ら育つ
学校とは違う異年齢集団で様々な経験を重ねることで、子ども自身が自ら育つことを成果とします。自分で考えて行動できるようになったり、自分が興味を持ったことについて深掘りする、自ら学ぶ姿勢が育まれてくれることを期待します。

「子供の楽園」と表された日本人の子育て
理想は、開国して間もない日本を訪れた外国人の手記や日記の記録にあるような江戸時代の「子供の楽園」と表された日本人の子育てです。「日本が子供の天国であることをくりかえさざるを得ない。世界中で日本ほど、子供が親切に取り扱われ、そして子供のために深い注意が払われる国はない。ニコニコしている所から判断すると、子供達は朝から晩まで幸福であるらしい」。(参考文献『逝きし世の面影』渡辺京二)当時の様子は本でしか知り得ませんが、活動を通じてまずは大人が変容を遂げ、今まで以上に母も父も子とコミュニケーションを図ることができたら、それらを取り戻すことはさほど難しくないだろうと楽観しています。
また同じく渡辺京二『近代の呪い』の、「人間が自然と交感するというのは、山川草木を含めてあらゆる存在を生命とみなし、その中で生死する自分の運命を納得するということです。昔は、聖人賢人でなくとも、あらゆる凡人にできたことでした。」にある、つい最近まで当たり前だった自然と交感することができる価値観を持つ子どもに育てます。土に触れ、地域の伝統を身につけることにより、昔の人たちが当たり前にしてきた感覚を取り戻せるのではないかと考えています。
100年前の当たり前を取り戻す「寺子屋 百(もも)」代表 金子知映